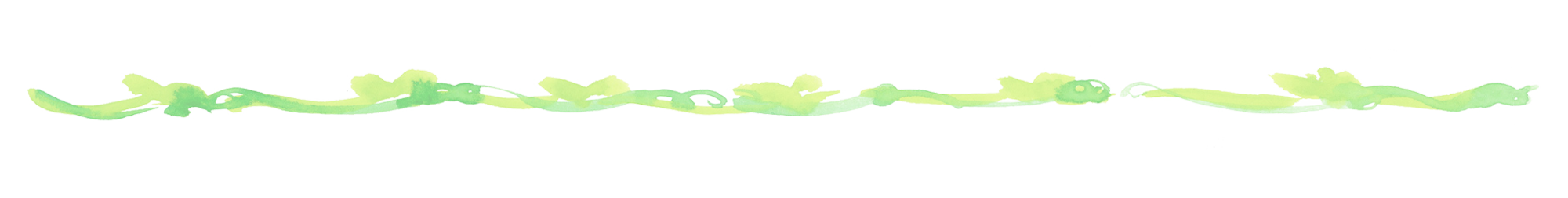
換気及び保温等
項目一覧
1.換気
換気の基準は、二酸化炭素の人体に対する直接的な健康影響から定めたものではありません。
教室内の空気は、外気との入れ換えがなければ、児童生徒等の呼吸等によって、二酸化炭素濃度が増加し、他の汚染物質も増加することが考えられます。
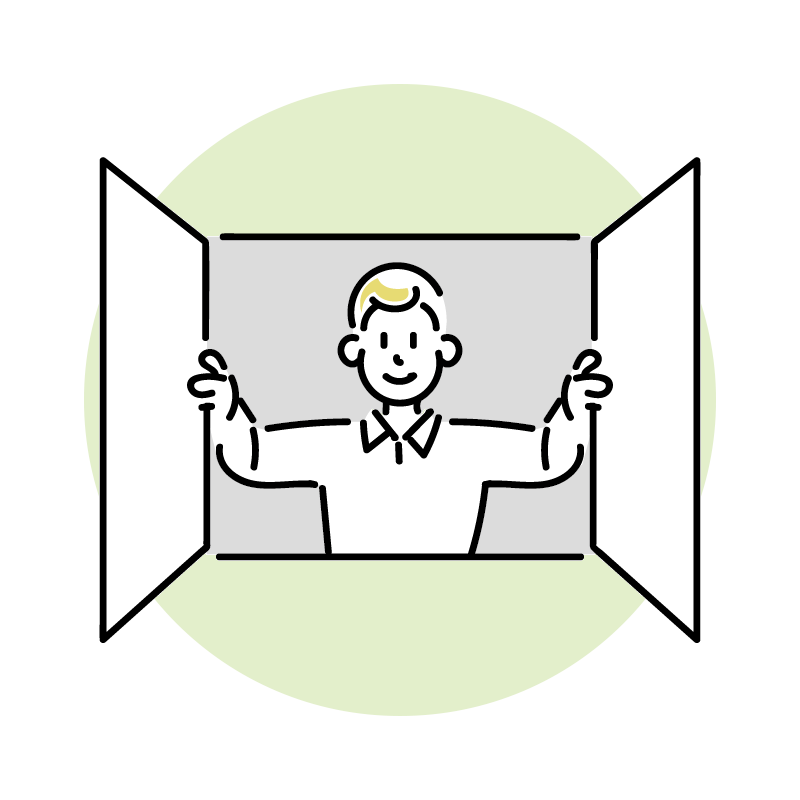
| 検査回数 |
|---|
| 年2回 |
| 基準 |
|---|
| 換気の基準として、二酸化炭素は、1500 ppm 以下であることが望ましい。 |
事後措置

二酸化炭素濃度が 1,500 ppm を超えた場合は、換気を強化します。
機械による換気が行われていない教室等においては、窓や欄間、入り口の戸等の開け方を工夫し、自然換気が適切に行われるようにします。
機械による換気が行われる教室等においては、運転時間の検討や工夫を行った上で、換気能力の確認等、機械の点検や整備を行います。
2.温度
温度は、健康的で快適な学習環境を維持するための指標のうち最も馴染みのあるものです。
児童生徒等に生理的、心理的に負担をかけない学習に望ましい条件として、健康を保護し、かつ快適に学習する上で維持されることが望ましい温度の基準が定められています。
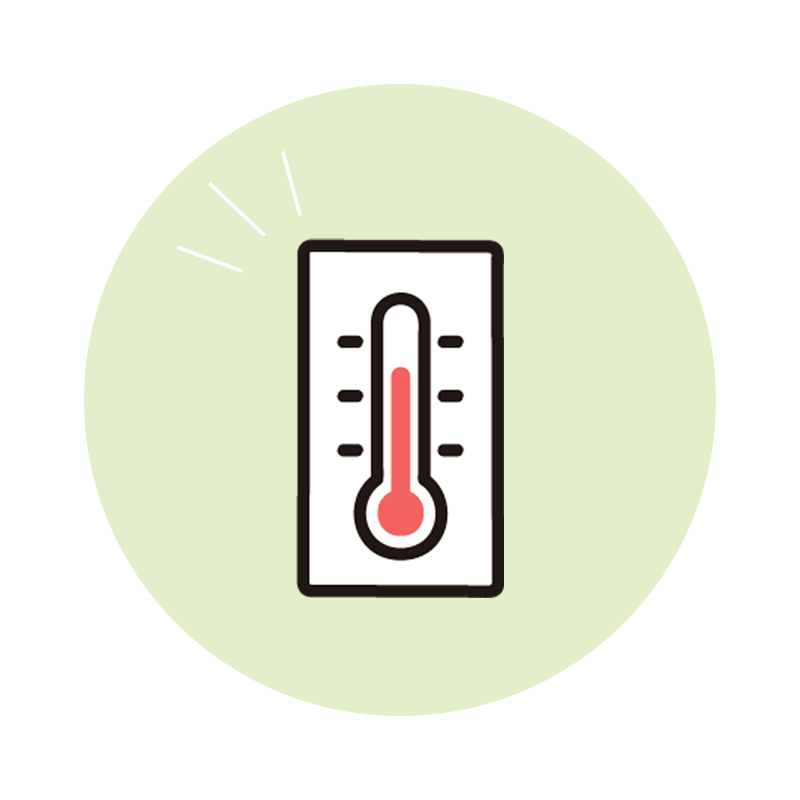
| 検査回数 |
|---|
| 年2回 |
| 基準 |
|---|
| 18℃以上、28℃以下であることが望ましい。 |
事後措置
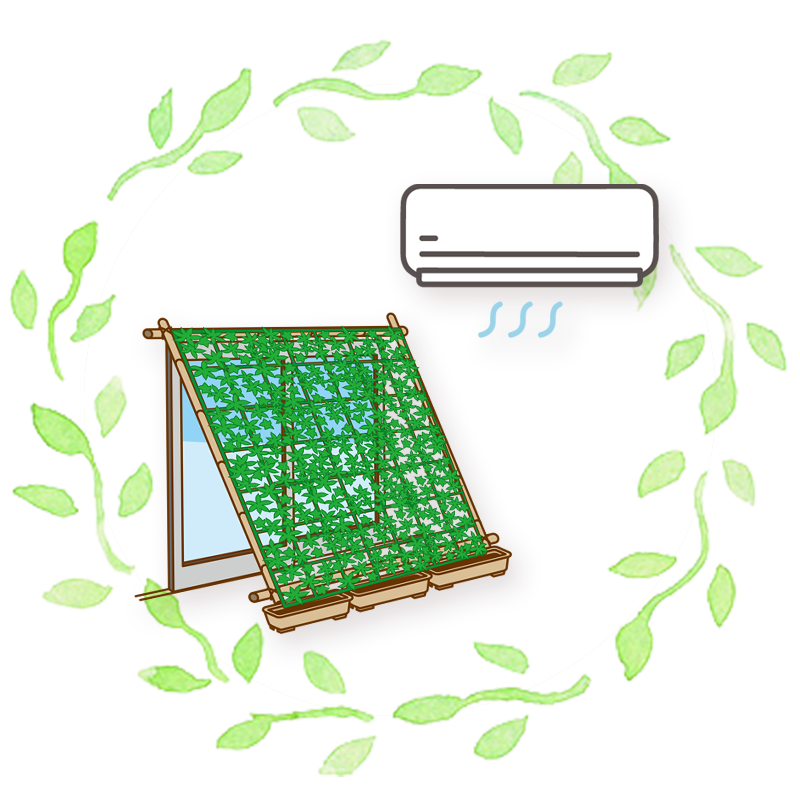
窓側の温度が高い場合の対策としては、カーテンの使用、ひさしの設置やツル性植物による壁面緑化(緑のカーテン)等により外気の影響(日射や温度)を受けにくくすることがあります。
なお、教室等において、冷房及び暖房設備を使用する場合は、温度のみで判断せず、その他の環境条件や児童生徒等の健康状態を観察した上で判断し、衣服による温度調節を含め、適切な措置を講ずることが重要です。
3.相対湿度
相対湿度は、空気中の水蒸気量をその空気の含むことのできる最大限の水蒸気量(飽和水蒸気量)で除して百分率(%)で示したものです。
一般的には、人体にとって最も快適な相対湿度の条件は 50 ~ 60%程度ですが、夏は高湿、冬は低湿である日本の気候の特徴を考慮し、学校環境衛生基準では教室内の相対湿度は「30%以上、80%以下であることが望ましい。」としています。
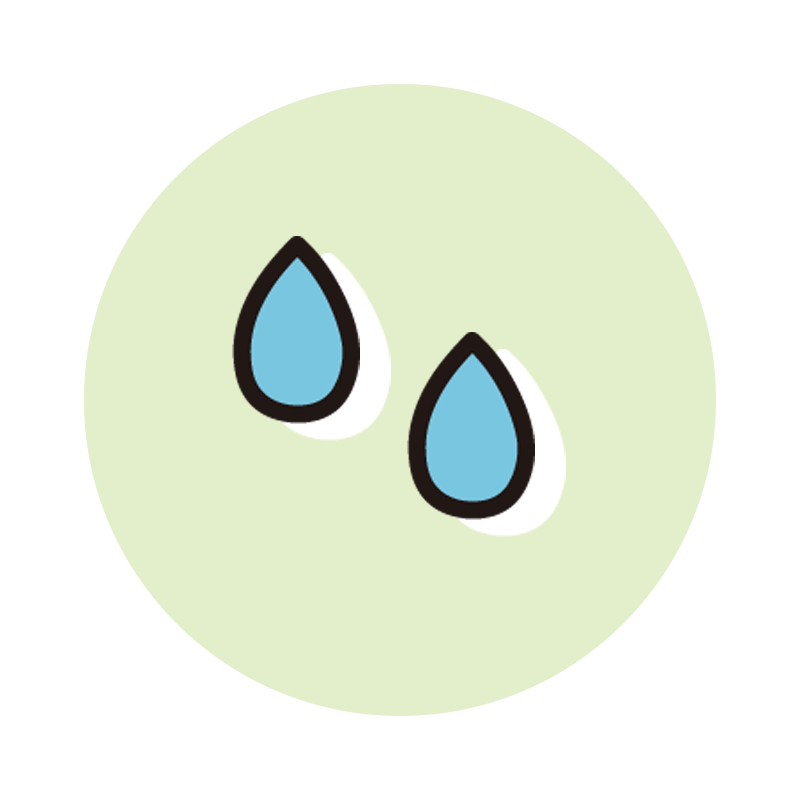
| 検査回数 |
|---|
| 年2回 |
| 基準 |
|---|
| 30%以上、80%以下であることが望ましい。 |
事後措置
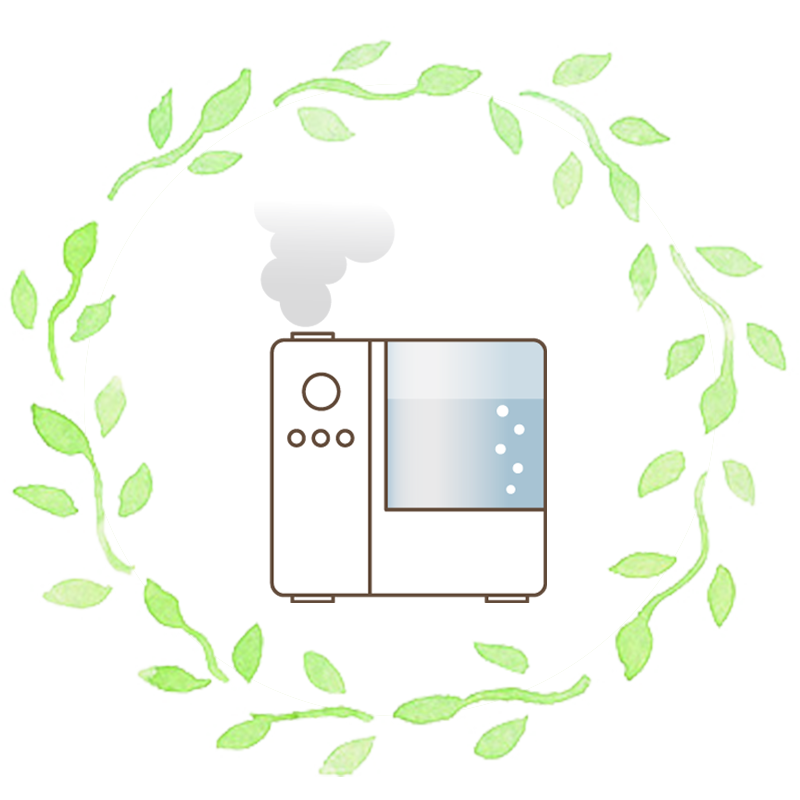
相対湿度が 30%未満の場合には、適切な措置を講じます。
なお、加湿器を使用する場合は、結露が生じ、カビが発生しやすくなることから、過度な加湿には注意する必要があります。
また、加湿器のフィルター等にもカビや細菌が発生しやすいことから、加湿器には水道水(塩素処理されており、雑菌が繁殖しにくいため)を使用し、定期的に清掃するなど、メンテナンスを適切に行うことが重要です。
4.浮遊粉じん
浮遊粉じんは、人体の呼吸器へ直接影響を及ぼすとされる空気中に常に浮遊している微細な物質のうち粒径 10μm 以下の粒子を検査対象としています。
教室等における浮遊粉じんとして、たばこの煙、チョークの粉や土由来のほか、外気に由来するものが考えられます。

| 検査回数 |
|---|
| 年2回 |
| 基準 |
|---|
| 0.10 mg/m3 以下であること。 |
事後措置

0.10 mg/m3 を超えた場合は、その原因を究明し適切な措置を講じます。
換気方法や掃除方法等を改善することも必要です。
たばこの煙が原因となることから、学校においては受動喫煙を防止するために必要な措置を講じます。
チョークの粉が浮遊粉じんの原因の一つです。
チョークには硫酸カルシウム(石膏)製チョークと炭酸カルシウム製チョークがありますが、炭酸カルシウム製チョークは、硫酸カルシウム製チョークと比較して粒子の比重が大きく、チョークの粉の飛散が抑えられます。
上履きに履き替えないで土足で教室を使用している場合は、校舎に入る際にマットで靴底の汚れを落とす指導や床拭きをするなど、土由来の粉じんを抑えるように配慮します。
外気が原因と考えられた場合、自治体の環境部局等と相談します。
5.気流
人体の快適性の観点から、室内には適度な空気の動きが必要ですが、強い気流は不快感を伴うものです。
窓等の開放による自然換気の場合でも適度な気流が必要ですが、冷暖房機等の使用時には、室内は 0.5 m/ 秒以下であることが望ましい気流です。
なお、教室の居住域(床から人の呼吸域の高さの範囲)では 0.2 ~ 0.3 m/ 秒前後が最も望ましい気流です。
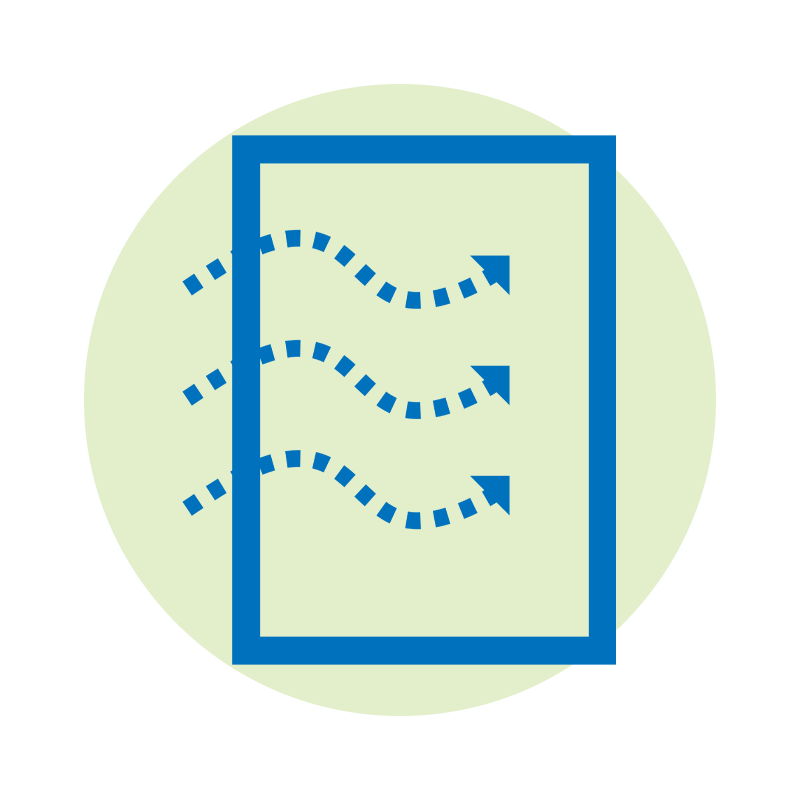
| 検査回数 |
|---|
| 年2回 |
| 基準 |
|---|
| 0.5 m/ 秒以下であることが望ましい。 |
事後措置
0.5 m/ 秒超の気流が生じている場合は、空気の温度、湿度又は流量を調節する設備の吹き出し口等の適当な調節を行うようにします。
6.一酸化炭素
一酸化炭素は不完全燃焼に伴って発生し、暖房の方式や車の排ガスからの影響もあり、濃度が高い場合には直接人の健康に影響します。

| 検査回数 |
|---|
| 年2回 |
| 基準 |
|---|
| 6 ppm 以下であること。 |
事後措置

6 ppm を超えた場合は、その発生の原因を究明し、適切な措置を講じます。
発生源として 考えられるのは、主に室内における燃焼器具の使用です。
窓が閉め切られた状態で自然排気式(CF 式)ボイラーと換気扇を同時に使用し、室内の圧力が室外よりも低下したため、一酸化炭素を含むボイラーの排気が正常に室外へ排出されず室内 の一酸化炭素濃度が上昇し事故に至った例が報告されています。
学校内に自然排気式(CF 式) ボイラーが設置されている場合には、換気扇との同時使用を避け、適切な換気が行われるような措置を講じます。
また、屋外式のボイラーへの交換を促進します。
7.二酸化窒素
二酸化窒素は、灯油等の化石燃料の燃焼に伴って発生します。
室内では、燃焼ガスが室内に放出される石油ストーブや石油ファンヒーター等の燃焼器具が発生要因となります。
空気汚染物質としての二酸化窒素は、高濃度で呼吸器に影響を及ぼすものであり、大気環境では光化学オキシダントの原因物質として知られています。
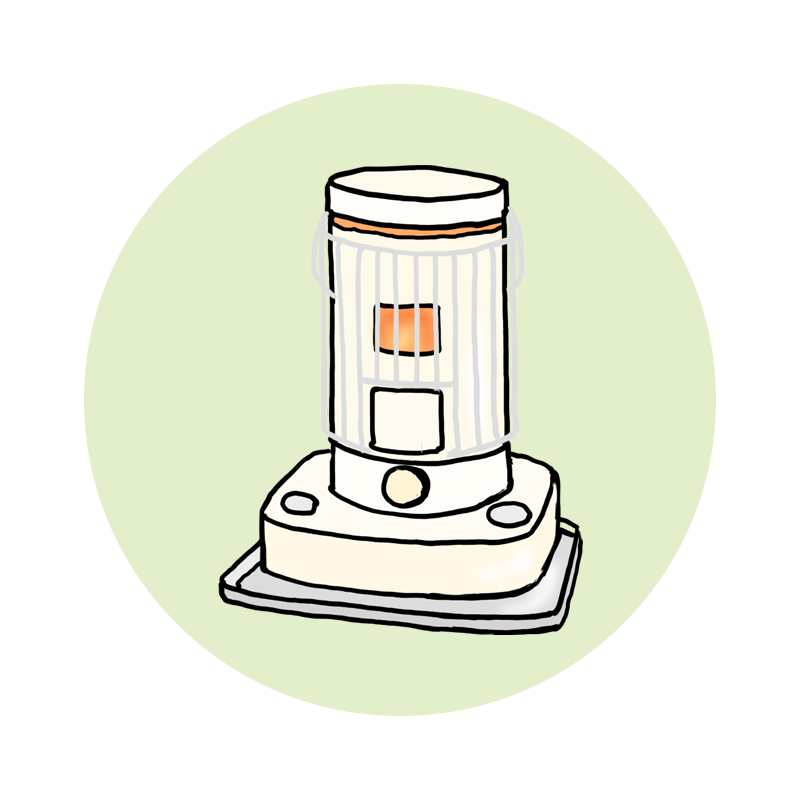
| 検査回数 |
|---|
| 年2回 |
| 基準 |
|---|
| 0.06 ppm 以下であることが望ましい。 |
事後措置

基準値を超えた場合は、その発生の原因を究明し、換気を励行するとともに、汚染物質の発生を低くする等適切な措置を講じます。
外気の二酸化窒素も検出されるので、外気濃度にも注意を払う必要があります。
周辺の交通量が多い学校では、外気濃度の測定に努め、外気の濃度が高い場合は、自治体の環境部局等に相談します。
8.揮発性有機化合物
揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)は、蒸発しやすく(揮発性)、大気中で気体となる有機化合物の総称です。
各種揮発性有機化合物は、室内の建材や教材、塗料や備品等から発生し、児童生徒等が学校で不快な刺激や臭気を感じ、状況によってシックハウス症候群の発生要因になるとされています。
| 検査回数 | |
|---|---|
| 年1回 | |
| 基準 | |
| ホルムアルデヒド | 100μg/m3 以下であること。 |
| トルエン | 260μg/m3 以下であること。 |
| 検査回数 | |
|---|---|
| 年1回(※必要と認める場合) ※必要と認める場合とは、キシレン、パラジクロロベンゼン、エチルベンゼン、スチレンの使用が疑われる場合 | |
| 基準 | |
| キシレン | 200μg/m3 以下であること。 |
| パラジクロロベンゼン | 240μg/m3 以下であること。 |
| エチルベンゼン | 3800μg/m3 以下であること。 |
| スチレン | 220μg/m3 以下であること。 |
事後措置
基準値を超えた場合は、その発生の原因を究明し、換気を励行するとともに、汚染物質の発生を低くする等適切な措置を講じます。
都市部に位置する学校は、外気の汚染物質の影響を受ける場合があります。
外気濃度の測定は、学校周辺に検査対象となる化学物質を取り扱う工場等がある場合に行い、外気濃度が高い場合は、自治体の環境部局等に相談します。
9.ダニ又はダニアレルゲン
近年、アレルギー症状のある児童生徒等が増加しています。
ダニ又はダニアレルゲンは、アレルギーを引き起こす要因の一つであることから、健康で快適な住居環境を維持するためにダニやダニアレルゲン対策が重要です。
学校においては、保健室の寝具や教室等に敷かれたカーペット等でダニ数やダニアレルゲン量が多いとの報告もあり、保健室の寝具、カーペット敷の教室等、ダニの発生しやすい場所について検査します。
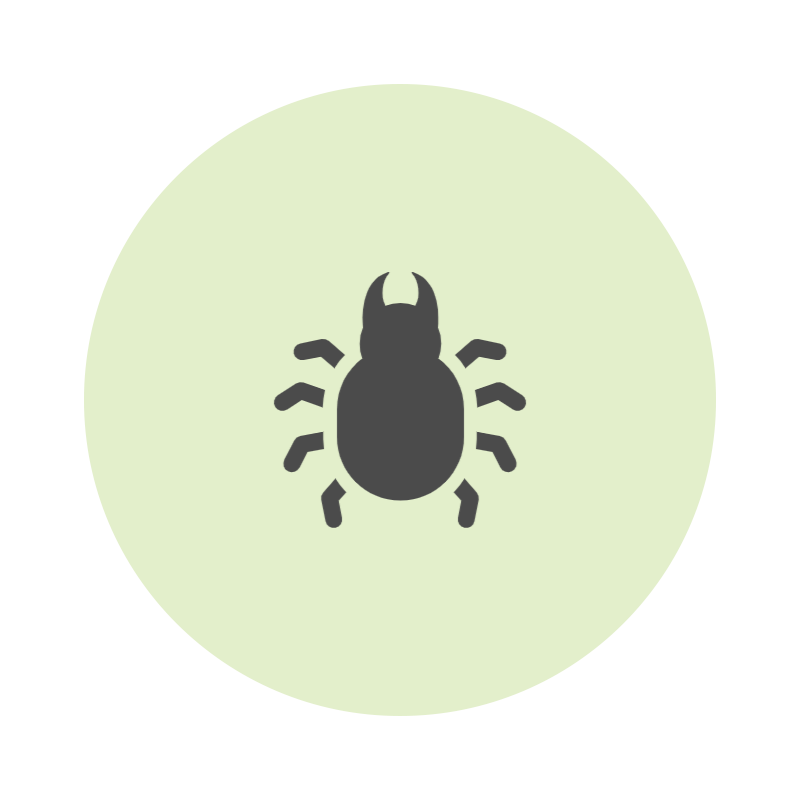
| 検査回数 |
|---|
| 年1回 |
| 基準 |
|---|
| 100 匹 /m2 以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。 |
事後措置

基準値を超える場合は、電気掃除機を用いて日常的に掃除を丁寧に行う等、掃除方法の改善を行います。
その際、集じんパックやフィルター等の汚れの状況を確認し、電気掃除機の吸引能力が低下しないように注意する必要があります。
保健室等の寝具や幼稚園等において午睡用に使用する寝具は、定期的に乾燥を行います。
また、布団カバーやシーツを掛け、使用頻度等を考慮し適切に交換します。
のり付けすることによって、布団の中からのダニの出現を防ぐことができます。